医療事故・医療過誤・医療ミスについて弁護士に相談したい患者さん・ご家族さまへ。主に近畿圏(兵庫・大阪)で活動しています。
もしかして医療事故かも…?
一度、弁護士に相談して
みませんか。
医療事故、医療過誤、まず何をしたらいい?
「医療事故・医療ミスにあったかもしれない」と思ったら、患者と家族はまず何をしたらいいの? 6つのアドバイスがあります
まずは、詳細なメモを作っておきましょう
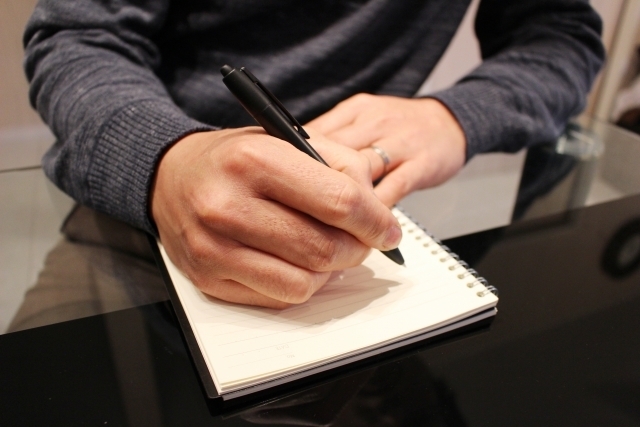
まずは記録です。当時に作成したメモは後日大変役に立ちます。次のようなことを思い出して、今のうちに書き出しておきましょう。できるかぎり、日付や時刻を明らかにしておくとより安心です。
解決されたお客様さまからのお声でも「最初に、このような事態に至った経緯をできるだけ詳細にまとめることが重要だと思います。私たちは医療行為に関する知識が少ないことがほとんどかと思いますので、思い出せる範囲でいいので、医療機関との会話や対応を時系列にまとめることがよいと思います。」とのメッセージが寄せられています。医療事故・医療過誤かも、と思ったら、まずメモを!!
何をメモしておいたらいいですか?
- 既往症、従前の治療や説明内容、投薬の内容
- それまでどのような経過だったか
- 事故の前に、医師から受けた説明や、見通し
- 事故と思われることが起きた時期、発生した時の状況
- 事故と思われることについて、医師からどのような説明を受けたか。(特に、最初の見通しと異なる結果になったことについて、どのような説明を受けたか。)
- その後の治療の内容
- 事故の後に転院するなどして別の医師にかかった場合、転院先での治療や説明内容
意外と役に立つその他のもの
医療事故でご家族が亡くなったかもしれない時に考えること~本当に申し上げにくいのですが、可能であれば解剖を、またAi(オートプシー・イメージング)を
解剖、っていきなり言われても受け止められないけれど…
私は、ご家族が亡くなった直後に、緊急でご相談を受けることがあります。
「医療事故調査制度」による死因の究明

2015年10月より「医療事故調査制度」が新たに始まり、この制度によって、診療関連死の原因解明が中立・公平に行われることが期待されています。
医療事故調査制度は、医療事故が起きた際、当該病院で事故調査をすることを義務づけ、得られた事故情報を集積して啓発することで、再発防止につなげようとするものです。
ただし、この制度は、診療機関における死亡や死産全てに適用されるものではなく「当該病院等の管理者が予期しなかったもの」に限られています。医療事故として調査するかどうかは、遺族の申し出の有無などではなく、医療機関の管理者が決める仕組みになっています。
このような制度の仕組みから限界はありますが、ご家族が亡くなった時、ご遺族としては、まずは医療機関へ「医療事故調査制度」によって調査をするように申し入れることを検討されるとよいと思います(当職は、この時点から、依頼を受けて代理人として活動することもしています。)
※より詳しく知りたい方はこちらへ 医療事故調査制度について
病理解剖
上記の医療事故調査制度によらなくても、死因や病因、病態を解明するためになされる「病理解剖」をして死因を明らかにしておくことが強く望まれます。病理解剖は、医療機関側から勧められることもありますし、ご遺族から医療機関に申し出ることによっても行われます。
司法解剖
ご遺族が告訴するなどによって、刑事事件として取り扱われ、犯罪捜査の一環としてなされる解剖は司法解剖です。これは、裁判所の許可を得てなされます。司法解剖は、遺族であっても、解剖結果の入手が長期(最も長い場合は5年)にわたって困難となるため、おすすめしません。
具体的に、解剖の有無が問題になったケース
解剖をしなかったために事実があいまいになってしまうケースは多くあります。
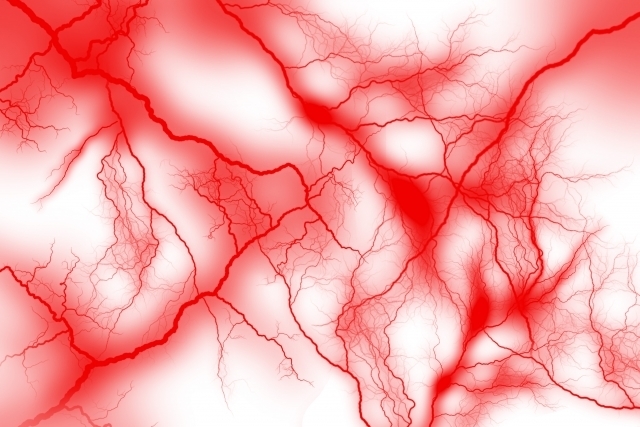
私が担当したケースで、脳内の主要な動脈の走行に異常があったかどうか、という点が争点の一つになっていたことがあります。ご本人様は、事故後も懸命に闘病されていましたが、訴訟中に亡くなりました。この時、病院から病理解剖を勧められ、また、当職からも解剖をお勧めしたのですが、ご家族が積極的なお気持ちになれなかったため、解剖をしないまま葬儀を終えたのです。そのため、ご本人様の脳血管走行に異常があったのかどうかは、分からないままとなりました。
その後、訴訟で相手方から「医師が解剖を勧めたのにこれを断り、本件の原因を解明する機会が失われた」という内容の書面が提出されました。このケースは途中で勝訴的な和解で終了しましたので、争点についての裁判所の判断はされていません。しかし、家族が拒否して解剖できなかった、ということが、後に患者の不利益に働く可能性も考えられます。
解剖で全て分かるわけではありませんが…
ご遺体を傷つけない、オートプシー・イメージング(Ai)による把握の方法もあります
通常の検査で「CT」や「MRI]を使って、病変を確認することはよく行われていますが、ご遺体に画像検査を行うことで、ご遺体にどのような器質性病変を生じているかを判断することができます(死亡時画像診断:オートプシー・イメージング)。このオートプシー・イメージングも、医療事故調査制度における調査方法のひとつとして挙げられており、解剖によるご遺体の損傷を回避したいとお考えの場合は、まずはAiの実施を医療機関に申し入れをすることができるでしょう。
ただ、通常の医療機関で、日常の患者さんの検査に使われている画像検査を、ご遺体に使うのは事実上難しい点もあります。通常の診療がされている医療機関で、他にも検査をお待ちの患者さんが多数いらっしゃる中にご遺体を運び込むのも計画がなければできません。また、Aiの読影については(通常の患者さんに対する読影とは異なる)特別の知見も必要なので、読影についても調整が必要ではあります。
医療事故・医療過誤かもしれない、というとき、誰に相談したらいいの?~行政窓口ではなく弁護士へ!
医療事故・医療過誤かもしれない、と思っても、誰に相談したらいいか分からない、ということがあると思います。まずどこに相談したらよいのでしょう。
「医療安全相談センター」が浮かびますが…
「行政で対応できないこと」があります
最初に、役所(行政)に相談に行く方も多いように思います。
医療法6条の規定に基づいて、全国各地に「医療安全相談センター」が設置されており、医療に関する相談を受け付けています。(兵庫県の場合、兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市の5か所に窓口が設置されています。)
医療安全相談センターは「医療機関に関する相談や不安等をお伺いし、助言や協力をする」という機関なのですが、相談できる内容に限りがあり、
- 医師の判断・検査内容の是非に対する判断
- 医療行為における過失や因果関係の有無、責任の所在の判断
- 医師や医療機関との紛争の仲介や調停
はセンターでは対応できない、と明記されています。(詳しくは「兵庫県/医療安全センターのご案内」をご覧ください。)
実際、医療安全センターへ相談に行ったけれども、相談の内容から「これは弁護士に相談してください」と言われ、私のところにお越しになった方もいらっしゃいます。
「医師の判断・治療に問題があったのではないか?」というときは直接弁護士にご相談ください
医療事故・医療ミス、自分で交渉できる?
カルテ開示の制度があるから、自分で交渉もできるのでは?

医療機関との交渉をご自身でされる方もいらっしゃいます。当職のところにも「途中まで自分で病院と交渉してみたのですが、全然進まなくなってしまって…」と、交渉の途中からご相談をされる方もいらっしゃいます。
確かに、カルテ開示の制度が浸透するようになってから、ご自身でカルテを入手して、交渉を始めることは可能になっていると言えます。
弁護士による精査
しかし、相手方医療機関に対して、責任(損害賠償請求)を認めさせるためには、①なされた医学的処置を明らかにし、②それが医療水準に照らして法律上の過失や因果関係があると言えるか、ということをよく検討してから交渉に臨まなくてはなりません。
カルテを取得することで①はある程度分かりますが、②は医学文献を調べ、それを法的に検討しなくてはならず、一般の方には相当ハードルが高いと思います。
実際、「ここまで交渉したんです」などと、ご本人様がなされた交渉の際の録音メモなどを見せていただくことも多いのですが、話し合いと言っても、詳細な診療経過の把握が不十分なままであったり、権利義務関係の話し合いになっていないなど、ただ感情論のやりとりのみに終始していることも多いように思います。
相手方医療機関との間で、効果的な話し合いをするためには、やはり、弁護士に依頼し、カルテ等の記録を精査の上、法律的な問題点を検討した上で臨むのがよいと思います。
弁護士に相談するタイミング
「なるべく早いうちに!」理由が二つあります

では、弁護士に相談するのはいつがよいのでしょうか。
医療機関の処置等に疑問を持ちながらも、親しい人にも相談できず一人で悩んだり、「こんなことで弁護士に相談してよいのだろうか」と悩んだりしているうちに時間が過ぎてしまう、ということもあると思います。
しかし、弁護士の立場から申し上げると、ご相談は「なるべく早いうちに」お越しになることをおすすめします。
 カルテ等の保存期間
カルテ等の保存期間
診療録(カルテ)の保存期間は5年と定められています。これを過ぎた場合、後から調査をしようとしても、医療機関にカルテがない、ということで、十分な調査ができない場合もあります。
 記憶があいまいになってしまう
記憶があいまいになってしまう
事故から時間が経ってしまうと、ご相談者・ご本人様も、また、医療機関担当者の記憶もあいまいになってしまい、何があったのかを明らかにすることが難しくなる場合があります。
このようなことから、「医療事故かもしれない」と思ったら、なるべく早く弁護士に相談することをお勧めします。
だいぶ時間が経ってしまったのですが…
なるべく早く、とは申し上げましたが、
「もしかして、あれは医療過誤だったのではないか…?」
こんな気持ちを持ちながら、どうしていいか分からず悩み続け、気がついたらずいぶん時間がたってしまった、ということもあると思います。
特に、事故によって重い障害を負ったような場合は、ご本人様もご家族様も日々を懸命に生きることで手一杯で、損害賠償請求のことまでとても手が回らない、というのが実際のところだと思います。
でも、私が伺った中で、かなり過失が明白で損害賠償請求が可能と思われるケースで、ご相談に来られた時点で、時効期間を大幅に経過していた、ということもあり、大変残念に思われたことがありました。
上記のとおり、法定のカルテの保存期間が5年であること、時間がたつと記憶があいまいになってしまうこと、また、調査には時間を要することからも、もし、もやもやしたお気持ちを抱えていらっしゃるのであれば、お早めに動かれた方がよいでしょう。
弁護士はどうやって見つけたらいいですか?

医療事故について弁護士に相談するとしても、特に弁護士の知り合いもいないし、誰に相談したらよいのか分からない、ということがあると思います。以前、遠方からいらしたご相談者の方が「今はホームページもたくさんあって、弁護士のホームページもたくさん見たのですが、それでも医療事件を積極的に取り扱っている方が誰か分からなくて…」と仰っていたのが印象的でした。
医療事件は、裁判までとなると、解決までに数年の時間がかかります。その間、依頼者と弁護士は互いに信頼関係を維持しなくては、続けることができません。そこで最も大切なのは、信頼できる弁護士を探す、ということになります。
 信頼できる弁護士がいれば、その方にまず相談
信頼できる弁護士がいれば、その方にまず相談
もし、どなたか信頼できる弁護士とつながりがあれば、まずその方に相談して、弁護士を紹介してもらうのがお勧めです。直接つながりのある先生が医療事件を取り扱っていなくても、神戸くらいの規模ですと、弁護士同士で、誰がどのような仕事が得意か、という情報を持っていることが多いので、その先生から紹介してもらうのです。弁護士間の紹介は一番信頼できると思います。
なお、この「弁護士間の紹介」というのは、単に「そのことなら○○先生が詳しいと思うよ」と言われて終わり、ということではなく、その先生自ら○○先生に連絡をして直接に紹介を受ける、ということを指します(狭義)。
 弁護士会で紹介してもらう
弁護士会で紹介してもらう
兵庫県弁護士会の総合法律センターでは、医療事件の取扱をしていると自ら申し出た弁護士の名簿があり、そこから弁護士を紹介してもらうことができます(弁護士紹介)。ここで紹介を受ければ、面談した弁護士から「私は医療事件は取り扱っていません」と言われるミスマッチを防げます。
 弁護士検索サイトは信頼できますか
弁護士検索サイトは信頼できますか
最近は、各種の弁護士検索サイトで、医療過誤事件を取り扱う弁護士を探すこともできるようです。ただ、これらは、上記の弁護士会での紹介と同様、自己申告によるものです。また、検索結果も、当該検索サイトに対して月額料金を支払っている弁護士に優先的に誘導する仕組みになっています。
 各種研究会に所属している弁護士を探す
各種研究会に所属している弁護士を探す
医療事件は、そもそも証拠となる記録すら手元にない上、医学的知見について立証してゆくことには大変な努力と工夫が必要です。そこで、患者側に役に立つ文献や鑑定書、和解事例、また、助言をしてくださる協力医の情報交換、また、判例に関する研究などが欠かせません。このために、各地で医療事故の患者側代理人が集まった研究会があります(神戸の場合は兵庫医療問題研究会)。また、名古屋には、全国の患者側弁護士によって作られている医療事故情報センターがあります。これらの会員(特に医療事故情報センターの正会員)になっている弁護士であれば、医療過誤事件を取り扱っている弁護士であるといえるでしょう。
 複数の弁護士に会ってみる
複数の弁護士に会ってみる
医療事件を取り扱っている弁護士の中でも、考え方や事件の進め方は、当該弁護士によって多少違うところがあります。そこで、比較検討のためにも、また、信頼関係が築けるかを考えるためにも、複数の弁護士に会って、実際に相談してから決めることをお勧めします。
解決したお客様からの声にも、複数の弁護士に会ってみることをお勧めされている方がいらっしゃいます。
◆2020.2.15追記
Q&Aよくあるご質問 の中に「弁護士はどうやって選べばいいの?」という別項目を作りました。そちらも併せてご覧ください。
◆2024.12.30修正
(弁護士 小野郁美)
初回ご相談は、リモート(ZOOM)の方式でも承ります。
一度相談してみようかな? と思われましたら…

お一人やご家族だけで悩んでいると、ぐるぐると同じところを堂々巡りになってしまうことが多いと思います。勇気を出して、相談してみませんか。
実際に相談された方の感想 も参考になさってください。
受け付けは、24時間承っております。(土日祝日や休暇期間を除いて3営業日以内にご返信をしております。)
ごあいさつ

弁護士 小野郁美
「医療ミスにあったかもしれない…」そんな時は私にご相談下さい。尋ねやすい雰囲気で、分かりやすい説明を心がけております。
一度ご相談してみませんか。
ご相談された方の感想はこちら
経歴などはこちら
アクセス
住所
〒650-0015
神戸市中央区多聞通3丁目2番9号甲南スカイビル710
JR神戸駅、高速神戸駅(阪急・阪神・山陽)から徒歩2分
受付時間
相談申し込みフォームからの受付は24時間承っております。